秩父札所 19〜25番 2006.5.25 約21,000歩
前夜の豪雨は練馬区などで浸水さわぎを起こすほどであったが、今日は一転朝から五月晴れ。
今までは、札所はハイキングや芝桜見物の「おまけ」であったが、気が付けば既に34箇所中22箇所を回ったことになる。
こうなると、生来のコレクター癖が頭をもたげ、札所巡りのみを目的に19-25番を歩いた。
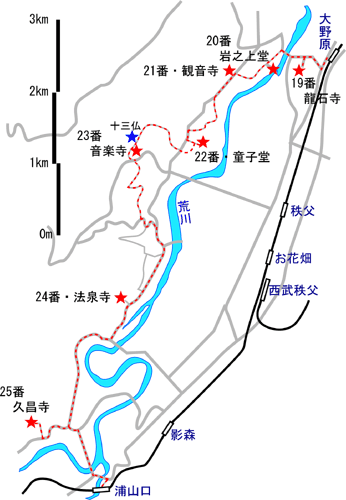
 |
大野原駅で降りる(秩父鉄道は本数が少ないので、事前に時刻を調べておこう)。 ■19番 龍石寺 大きな岩盤の上に立てられている。大昔、弘法大師が雨乞いの祈りを捧げた所、この岩の割れ目から龍が天に昇り大雨を降らせたとの言い伝えがある。本尊は室町時代のものとされ、昭和47年には本堂の修復が行われた。 門の反対側に六地蔵と意味不明ながら「子育て婆さん」のお堂あり。 20番へは荒川を渡る。川には新旧両方の橋が架かっているが、風情のある古い方の秩父橋をわたろう。交通量の多い車道の向こうに江戸巡礼古道があるので、そこを登る。途中の見晴らしも良く気持ちよい。    |
 |
■20番 岩ノ上堂  道路から見下ろした形のところにある。良い雰囲気。 道路から見下ろした形のところにある。良い雰囲気。堂は江戸中期の造営と思われ見事な彫刻がある。本尊は藤原時代のものとされている。  ここから後も古道を行く。20番から25番までの間、江戸時代や明治時代の巡礼古道が復活し歩ける。道端には江戸時代の道しるべが散在する。 ここから後も古道を行く。20番から25番までの間、江戸時代や明治時代の巡礼古道が復活し歩ける。道端には江戸時代の道しるべが散在する。古道の地図はこちら |
 |
■21番 観音寺 別名:矢の堂 八幡大菩薩の放った矢がこの地に落ち、悪魔が退散したとの言い伝え。今の堂は大正12年の火災で再建されたもの。 道の反対側には秩父歌舞伎の名優:中村十九十郎の墓がある。 ここから、県道をしばらく行くと、左へ明治古道が分かれる。、のびやかな田園風景が広がる。県道は結構交通量が多く古道を歩こう。    |
 |
■22番 童子堂  淳和天皇の弟、伊予親王の菩提寺として草創されたと伝えられる。わら葺の山門、周りの畑と雰囲気のある寺である。 淳和天皇の弟、伊予親王の菩提寺として草創されたと伝えられる。わら葺の山門、周りの畑と雰囲気のある寺である。23番へは県道を横切り「小鹿野道」を行こう。結構きつい山道であるが、これも修行とがんばろう。息が上がった頃に尾根にたどりつく。 ここには有名な13地蔵(十三仏)がある。13体の地蔵がはるか武甲山と秩父の町を見下ろしているようなシチュエーションで、ポスターなどの題材となる。ところが、ここは個人の所有地らしく、地蔵の前にはモダンな家が建ってしまって、いまいち見栄えが悪い(古いガイドブックの写真にはこの家はなかった)。  |
 右は鐘つき堂。明治27年の秩父事件の際は、この鐘を合図に一揆が始まった。 |
■23番 音楽寺 寺の周りは秩父ミューズパークと言うレクリエーション施設になっていて拓けている。山道をあえぎながら登ってきたのに突然ドライブ族が走りまわる別世界となり違和感を感じる。 本堂の左を更に登ったところに観音堂はある。 名前のせいか、絵馬を下げる場所には、演歌歌手のヒット祈願や、高校吹奏楽部の全国大会出場祈願などが多く掲げられている。と言うことで訪れる人も多いらしく、メジャーな存在らしい。門前にはお休処の飲食店も多く俗化した感がある。    ←レストランより ←レストランよりここからも江戸古道がのびる。但し山道で歩き辛い。20分も下るとドライブウェイを横切るが、目の前に「生ビール!」の幟が立つレストラン。意に反して足が勝手にレストランに向かい、気が付いたら生ビールを注文していた。このレストランからの武甲山の眺めは絶景。 ビールを飲んだせいか、どっと疲れが出て、もう山道を歩く気力は無い。県道を歩くことにする。 県道は歩道が無く歩きづらい。途中、外人とすれ違ったら、向こうから「コンニチワ」と声を掛けられた。 |
 |
■24番 法泉寺  道路からいきなり100段はあろうかと言う階段。後ろから来る、おばあちゃん達に追い越されてなるものかと、歯を食いしばってがんばる。上に着いた時は息切れしてぜいぜい。 道路からいきなり100段はあろうかと言う階段。後ろから来る、おばあちゃん達に追い越されてなるものかと、歯を食いしばってがんばる。上に着いた時は息切れしてぜいぜい。養老元年の創設。 25番までは約3KMと長い。途中武甲山が良く見える。 |
 |
■25番 久昌寺 通称:御手版寺 岩に抱かれたような立地。その昔、性空上人が閻魔大王から送られたという御手版を本寺に納めたのが起源。 ここから、秩父鉄道の「浦山口」まで行き、帰宅。 今日の札所めぐりで めでたく 1番から29番まで周ったことになり、後は30番から34番までのみ。但し、残りはみな各々が離れており、最低3回は必要か? |